地絡について [REPORT1-7] B種接地線に戻らない零相電流の謎
| (1)はじめに |
| (2)障害現象 |
| (3)平衡特性についての見解紹介 |
| (4)平衡特性の根本原因 |
| (5)マグネット三相不揃い投入について |
| (6)トランス2次側がΔ結線の場合の考察 |
| (7)おわりに |
地絡について [REPORT1-7] B種接地線に戻らない零相電流の謎
| (1)はじめに |
| (2)障害現象 |
| (3)平衡特性についての見解紹介 |
| (4)平衡特性の根本原因 |
| (5)マグネット三相不揃い投入について |
| (6)トランス2次側がΔ結線の場合の考察 |
| (7)おわりに |
- まず、当ビル電気系統図を問題の漏電が発生する部分を中心に示しておく。
- 上図の①~⑤の地点でリークモニタで3相一括で測定記録したデータを順に示しておく。
①排気ファン直前の分電盤入口
②、③のグラフと比べて値が小さいが、小口径クランプを使用しているのと、つまんだ電線が末端で細くなっており後で述べる平衡特性の影響が少ないためと思われる。
②1階西電気室ZCT負荷側
5時がEF-101の始動時間である。1時30分頃に測定値が高いのは、試しに中央監視盤から始動させた結果である。
③18階西電気室系統TW12-08出口
5時がEF-101で、6時45分は2階のAC-101始動時間である。後者の始動時の方が大きな零相電流を観測しているが、漏電警報は5時のEF-101始動時だけである。 漏電警報器の整定値は共に50mAと同じである。
④トランスTW12のB種接地線
5時、6時45分共に一切の零相電流の変化は認められない。
⑤当ビル電気設備のB種接地線の根元
本当の地絡時には大きな零相電流が測定されている。- 特にAC-101に注目すると、この空調機は通常約30Aの運転電流である。それが始動時以後常に約6mA程度の零相電流を観測している。これだけを見るとあたかも 絶縁不良で漏電しているのではないかと疑われても仕方ない。また始動電流は少し多めの通常電流の十倍としても約300Aと思われるが、約30mA程度の零相電流が 観測されている。値は小さいが、EF-101も同じように零相電流を観測している。
- H商工さんの技術リポートから抜粋
H商工さんは、問い合わせに対していつも丁寧にかつ詳しく回答してくれる。今回も無理を言って技術資料を送っていただいたので、一番に紹介する
----------------------------------------------------------------------------------------
……零相変流器の一次導体の配置により、各一次導体に流れる負荷電流によって零相変流器に生じる磁束が多少異なるため、実際に漏洩電流がなくても零相変流器の二次側に 若干の出力が出ます。(これを零相変流器の不平衡特性という)
従って電動機の始動時には、相当大きな負荷電流が流れるため、不平衡特性による零相変流器の二次出力も大きく出ます。この原因としてはZCT内部の磁性材料の特性、 あるいは巻線のバラツキによるものです。
Ia+Ib+Ic=0であっても、電流によって生じる磁束が Φa+Φb+Φc≠0となる場合、二次側に零相電流出力が生じます。これを残留電流と称しています。
……現在の零相変流器は、内部に使用している鉄心材料の特性がよくなっているため、不平衡特性の影響はほとんどなく、継電器を動作させることはありません。
----------------------------------------------------------------------------------------
このリポートでは「不平衡特性」という述語が使用されている。私見ではあるが、これを「平衡特性」と言い替えた方がいいように思われる。
通常電力系統では「残留電流」とは、3線のインピーダンス特に対地静電容量が不平衡で、対地電源電圧が平衡していても零相電流が流れる場合に、この零相電流を「残留電流」と 言っている。また逆に線路インピーダンスが平衡でも、V結線でSVRによる電圧調整を行った時などに対地電源電圧が不平衡になり、零相電流が流れる場合にこの電流を 同じように「零相電流」と称している。上記技術リポート で言う「零相電流」とは異なるので注意が必要である。- JISC-8374(漏電遮断器)の規定の概略
----------------------------------------------------------------------------------------
零相変流器の一次側に概ね定格電流の6倍(試験電流値は詳しく規定されている)の試験電流を1秒間通電する。三相3線式のものは、三相平衡試験電流を通じる。このとき 漏電継電器が不動作のこと。
----------------------------------------------------------------------------------------
このことはZCTのカタログや漏電警報器のカタログにはよく記載されている。H商工のZCTカタログもこの説明がしてある。- M菱電機技報による平衡特性
M菱電機技報2001年10月号から抜粋する。
----------------------------------------------------------------------------------------
一次電流の平衡状態にアンバランスが生じた場合にZCTの検出コイルの負担抵抗に電圧が発生し、その出力電圧の値によって漏電状態か否かを判断している。検出すべき漏電電流の 大きさは、人命保護の観点から30mA以上である。一方、地絡のない三相平衡状態においては、定格電流の6倍(例えば定格が225Aの製品では1350A)の一次電流がZCT 内を通過しても、検出コイルに発生する誤差出力を事故と判断して回路を開いてはならない。すなわち、ZCTの基本特性として、高感度な出力特性とS/N比で数万倍の平衡特性が 要求される。
----------------------------------------------------------------------------------------
ここでは平衡特性を、一次電流と誤差電流のS/N比で表している。- H谷川電機工業製のリークモニタの平衡特性
私が測定したリークモニタはH谷川電機製であるが、平衡特性の記述がなかったのでメールで問い合わせた。回答は概略次の通りである。
----------------------------------------------------------------------------------------
クランプCTの負担抵抗100オームの時、一時往復負荷電流100Aにおいて出力電圧AC0.5mV以下
クランプCTの負担抵抗が約200Ω、一次電流250mAのとき、出力電圧25mV±1mV
クランプCTの負担抵抗が約40Ω、一次電流1250mAのとき、出力電圧25mV±1mV
----------------------------------------------------------------------------------------
これを一次電流と誤差電流の比で表すと、10000倍となる。私が実際に測定した値も、一次電流300Aで誤差測定電流が30mAなので、きっちりつじつまが合う。- H置電機およびY河電気のカタログ
ここでは平衡特性という用語は使わず、直接「残留電流」または「残留電流の影響」で仕様表示している。
----------------------------------------------------------------------------------------
5mA(AC100A入力時)……H置電機9657の場合
100Aの流れる約Φ10mmの往復導体で12mA以下 ……Y河電機CL345の場合
----------------------------------------------------------------------------------------
これを一次電流と誤差電流の比で表すと、20000倍および約8300倍となる。
余談になるがH置電機の技術資料には、クランプセンサの入力部のタイプとして、よく使われている電圧出力タイプと共に、低シャント抵抗の電流出力タイプもあることが紹介 されている。- まとめ
ZCTおよびクランプ式リークセンサにおいては、一次電流が平衡していても一次電流の10000分の1前後の残留電流が発生し、見かけ上の零相電流すなわち誤差電流として 観測されてしまう。3相一括で漏れ電流を測定する時には十分このことを意識する必要がある。
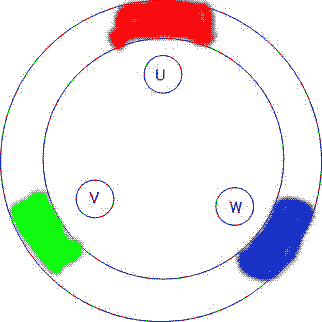
- モータを始動するのは多くの場合、モータ回路の直前にあるマグネットスイッチ(以後Mgと記す)が閉じることによっている。このMg投入の際三相同時は考えにくく、 若干の時間的ずれがあるのがむしろ自然である。これを投入不揃いと称しているが、負荷側から見ると瞬時的な断線と考えることも出来る。
- 断線の場合は対象座標法により零相電流が流れる。当初私はモータ始動時の漏電警報の原因はこれだと思っていた。しかし確信がないので、ある掲示板でこの問題をテーマに 議論をした。結論は不揃い投入による零相電流が原因ではない、ということに落ち着いた。この零相電流については、その掲示板でKiichiさんが端的にまとめておられる ので、紹介する。
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 1線断線時には、零相電流が流れます。零相電流の大きさは、零相インピーダンスに反比例します。
- 零相インピーダンスは断線点(今回の場合はMgの接点)から電源側をみた零相インピーダンス(Z01とする)と負荷側をみた零相インピーダンス(Z02とする)の 和になります。
- Z01は中性点B種接地抵抗値(REb)の3倍で3REbになります。(数十オーム程度?)
- Z02は絶縁抵抗値(線路・電動機含む)と対地静電容量のインピーダンスの合成インピーダンスです。(1MΩ以上と思われます)
- 零相インピーダンス Z0=Z01+Z02=1MΩ以上と思われ、1線断線に起因する漏電警報の発報ではないと考えられます。
- 上記の(2)障害現象の観測データを見ると確かにモータ始動時に顕著な零相電流が観測されているが、ここだけに目がいってはいけない。始動後の常時の零相電流値も少しでは あるが上昇している事実が重要である。つまり投入不揃いだとすると、投入時には確かに零相電流を観測するかもしれないが、定常状態になると元の値に戻ると考えられる。しかし このことはリークモニタでグラフ化しないと判定は難しいかもしれない。
- 結局Kiichiさんも言われているように、1線(2線でもよい)断線時の零相電流の大きさに注目するしかないようである。
- 数年前であるが、トランス2次側がΔ結線の200V系で今回と同じくある特定モータ始動時だけの漏電警報を、私は経験している。この時はリークモニタがなくアナログ型の クランプリークメータで測定したのであるが、モータ入口とB種接地線の両方で確かに零相電流を観測した。今回と同様にモータの絶縁も測定したが、絶縁不良とは考えられな かった。
- この項、以下推敲中